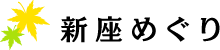「グリーンランドの日常」
立教大学 観光学部交流文化学科 3年 石川 祐羽
ぽつんと、シーソーがひとつ。
新座駅から立教大学新座キャンパスへ徒歩で向かう学生の通学路の途中にこの公園は位置している。北口の『いちげん』というお店の奥の駐輪場を通り抜け、旧川越街道をセブンイレブンのほぼ向かいの道へ渡ってしばらく行くとたどり着ける場所だ。名前は、グリーンランド児童遊園。グリーンランドねえ。公園の看板と公園を交互に見る。ここは外の道路より2メートルほどくぼんで作られていて、お堀みたいになっている。たしかにそのくぼみを作る坂の部分には緑、いや正しくは雑草が生えているけれど、グリーンランドなんてずいぶん美化した名前をつけたものだなあ。

園内に関しては、もうこの公園前を2年通っているのに、あとふたつくらいあったはずのシーソー以外の遊具が思い出せない。誰かが使っているのを見たことないからだろうか。しかしこんなことを言っておきながら、「グリーンランド」の光景に何度も温められてきたのはこの私なのである。私がこの公園を好きになった2つのシーンがあった。
ひとつはまだ明るい帰り道に目にした小学生の姿。私たちの頃よりもっと色の種類が増えたランドセルを背負って、子供たちが口々におしゃべりをしながら下校している。ある日、通学路に立って子供たちの帰りを見守る60代くらいの男性が、公園でランドセルをおろした男子小学生に声をかけた。「おかえり。」上からの声に遠慮がちに答える。「こんにちはあ。」「学校楽しかった?」「うん。」「今日は何したの?」「サッカーしたり、、、」「そっかあ、よかったねえ。」-誰が聞いたって特別な会話ではない。しかし私は公園前を通りすぎるほんの数瞬に見たのだ。男性の柔らかい顔と、男の子の照れくさそうな目。毎日この会話を繰り返しているのか、初めてなのかわからないけれど、はじめは他人のおじさんに話しかけられた警戒心をまとっていた男の子の目はこの数秒の間で嬉しさをにじませた。なんてことないことでも、誰かに自分のことを聞いてもらえたらなんか嬉しいよね。頭の中で男の子の気持ちを代弁してみた。

もうひとつは朝の公園で遊ぶ保育園の子供たちだ。朝のお散歩の途中なのだろう。3人ほどの保育士さんが優しい声をかけながら見守る中で、2、3歳の子供たちが思い思いに公園を楽しんでいる。きゃあという奇声がたびたび静かな住宅街に響いた。小さい子の笑った顔ってどうしてこんなにまぶしいのか。これは太陽のせいなのか。おそらくほっこりしている私の顔は子供たちと反対でとても渋くなっている。大学に入ってから抱えきれないほどいくつもの悩みがあった当時の私は、小さい子特有の喜びの奇声に少し救われた。悲しみでも怒りでも喜びでも、感じたものに対する反応をためらいなく表すことは、社会にもまれてどこかに落としてきた気がする。大人になると空気を読むからそう簡単にはできないが、抑えすぎていつのまにか自分にも示せなくなっていた。少し考えすぎていたのかもしれない。自分の中だけだったら奇声あげたっていいんだ。無邪気に思うままに遊ぶ園児たちの姿は意図せず私の気持ちを軽くしてくれた。

どちらも新座に住む人にとっては単なる日常のワンシーンに過ぎない。さらに言えばこんなことは世界中で普通に起こる出来事だ。しかし私にとっては、あのときあの場所でないと出会えなかった、悩みだらけの重たい私を包んだ数秒の「日常」。おおげさだと笑われても無理はない。同じ場面に出くわしても何も感じない人だっているはずだ。それでも、私たちの日常が誰かにとってとてつもなく大きな「日常」になること、それに気が付かせてくれたのはあの公園だった。いつか誰かが私と同じように、グリーンランドの日常を味わう日がくればいいなと思う。